中小企業M&Aの実務―「株式譲渡所得を徹底解説」

0.はじめに
株式譲渡所得の計算では、譲渡主体の違い(個人か法人か)によって取扱いが異なる部分もあります。このように、株式を譲渡した際に発生する譲渡所得の計算方法や確定申告、株式の事前とりまとめなどの各論点を解説します。
1.個人株主と法人株主の課税における相違点
ここでは、項目ごとに個人株主と法人株主の場合の株式譲渡課税の違いについて解説します。株主を譲渡する株主が個人であるか法人であるかによって、課税時に取り扱いが異なる点がいくつかありますが、株式譲渡所得の計算方法については、どちらも「株式譲渡所得=譲渡収入−株式の取得費―譲渡費用」といった計算式となり、基本的な考え方は同様です。
適用される税率について
非上場株式20.315%(所得税15%、住民税5%、復興税0.315%)
大法人(資本金1億円超)は、約29.7%
中小法人(資本金1億円以下)は、所得800万円以下の部分については約21%、800万円超の部分については29.7%
※(内訳は、法人税+地方法人税+住民税+事業税。地域によって若干の相違あり。)
株式譲渡所得の認識時点について
原則:引渡日 例外:契約の効力発生日
相対取引の約定が終了し成立し効力を有することとなった日。
譲渡時の取得費について
譲渡収入の5%が最低限認められる。
譲渡収入の5%とするいわゆる5%ルールはなく、会社の会計帳簿上記録されている取得原価を取得費とする。
相続開始後3年10ヶ月以内の特例
①株式譲渡所得の計算時に、譲渡株式に係る相続税を取得費に加算可能。
②非上場株式を発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税の適用はなく通常の株式譲渡所得課税の扱い。
適用されない。
譲渡費用における消費税の取り扱いについて
消費税込み。
法人の経理処理による。消費税抜き処理or消費税込み処理。
他の所得との通算
他の所得とは分離して所得計算する。非上場株式同士の譲渡損益の通算は同一年のみ可能とする。
譲渡損、譲渡益ともに他の所得と通算する。
繰越欠損金
非上場株式の譲渡損失は繰越不可。
繰越可。以下の各年に応じて繰越期間が異なる。
①H20.4以後終了事業年度発生分〜:9年
②H30.4以後開始事業年度発生分〜:10年
2.個人株主の株式譲渡所得の発生時点はいつなのか
株式譲渡所得の認識時点は、引渡日を原則となっていますが、例外として契約の効力発生日とすることも認められています。
契約の効力発生日とは、単純に契約締結日を指すのではなくて、その契約が効力を生ずる日を指します。株式譲渡契約書締結日と株式引渡日を一定期間あける場合には引渡日までの義務などのクロージング条件を課し、引渡日にこの条件を満たしていることを双方が確認を行って初めて株式譲渡が実行されるため、このようなケースでは契約の効力発生日と引渡日は同一日になります。
つまり、実務上は株式譲渡契約書上クロージング条件が課されている場合には、引渡日と契約の効力発生日は同一日になります。
(具体例)
- 株式譲渡契約締結日:令和8年1月
※株式譲渡契約書には、引渡日における双方のクロージング条件の充足確認を契約効力の条件に入れているものとする。 - 株式引渡日:令和8年3月
このようなケースの場合、引渡日は令和8年3月、契約の効力発生日も令和8年3月となり、所得の認識時点は令和8年3月となります。
3.個人株主が株式を譲渡する場合、譲渡所得計算上「取得費」はどう計算するか
個人株主の株式譲渡所得の金額の計算では、株式の「実際の取得費」と「譲渡収入×5%」のいずれか大きい金額を「取得費」とすることができます。財務体質がよく株価が高くつくような譲渡企業の株式譲渡の場合には、「譲渡収入×5%」を取得費とした方が有利となるケースも多いため、税額の計算上注意しなければならないポイントになります。また、株式の「実際の取得費」と「譲渡収入×5%」のいずれか大きい金額を選択することができる取り扱いは、実際の取得費が不明な場合だけではなくて、実際の取得費が明らかな場合にも適用することができます。
(ただし法人株主が株式を譲渡する場合には適用することができません。)
実際の取得費に含まれるものの例は下記の通りになります。
(1)金銭で購入した場合
- 実際に支払った購入代金
- 取得時の仲介手数料、契約書にかかる印紙代など
※上場株式と同様に、支出した実額が「取得費」になります。
(2)設立時や増資時に引き受けた株式
- 出資した金銭の額
- 出資が現物出資なら、その評価額
基本的には、払込金額(または現物出資評価額)が取得費となります。
(3)相続や贈与で取得した株式
被相続人の取得費を引き継ぐ(取得費の引継ぎルール)
贈与時点の時価(贈与税評価額)が取得費となる。
4.非上場株式を売却した際の確定申告について
(1)いつ確定申告・納付するのか
申告期間、納付期間は下記の通りになります。
申告期間
※土日祝でずれる場合あり
(例えば2026年だと、2月16日(月)〜3月16日(月)になる可能性があります。)
納付期限
申告期限と同じ日(3月15日頃)が納税期限です。
一括納付が原則ですが、口座振替を申し込めば4月中旬頃に自動引き落としが可能になります。
5.相続株式の譲渡に使用できる特例(取得費加算)とは
取得費加算の特例とは、相続や遺贈で取得した財産(不動産・株式など)を譲渡したとき、相続税で課税された部分を譲渡所得の取得費に上乗せできるという内容になります。相続税を既に支払っている財産を売却した場合、何も調整を行わなければ「相続税+譲渡所得税」で二重課税になってしまうため、二重課税になるのを防ぐために調整する趣旨になります。
(1)適用要件
(期限を超過した譲渡の場合、適用はできません。)
(2)加算できる額
加算できる相続税額は、その財産に対応する相続税額を「按分」して求めます。
相続税のうち、売却した財産に相当する部分のみを取得費に加算できる仕組みです。
(計算例)
取得費に加算できる額 = 相続税額 × (譲渡した財産の相続税評価額 ÷ 課税対象財産の合計額)- 相続税額: 実際に納付した相続税
- 譲渡財産の相続税評価額: 相続税申告で計算した評価額
- 課税対象財産の合計額: 相続税申告で計算した課税財産の総額
(4)確定申告で必要な手続きについて
確定申告でこの特例を使う場合、次の書類が必要になります。
- 相続税申告書の写し
- 相続税の納税証明書
- 取得費加算の特例に関する明細書
これらを添付して、譲渡所得の申告をします。
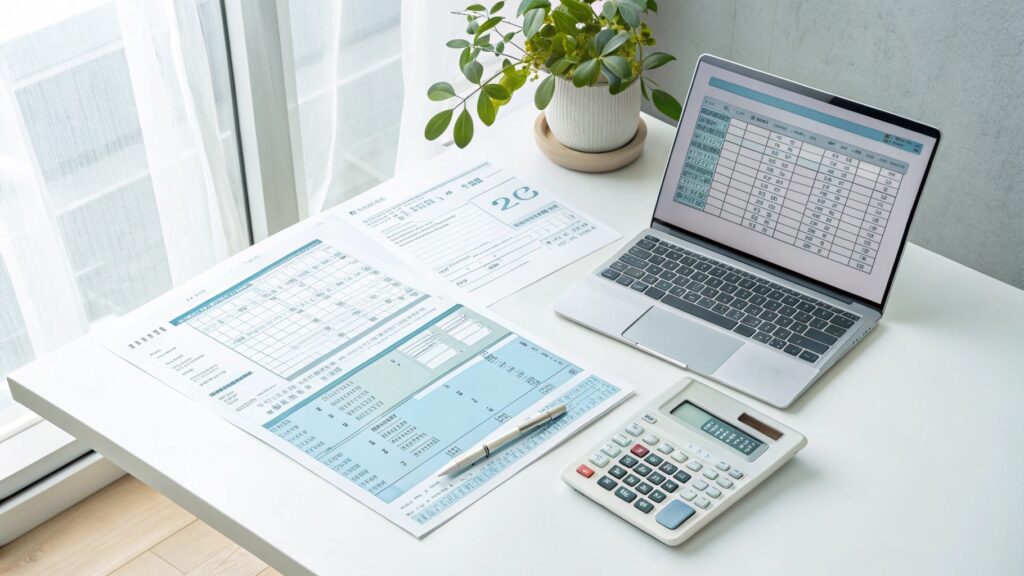
6.M&Aで発生する譲渡費用の取り扱いについて
譲渡費用とは、株式を譲渡するために直接かかった費用のことです。
譲渡所得の計算式は下記の通りとなります。
譲渡費用が大きいほど課税所得が下がり、税金も少なくなります。しかし、譲渡株主の株式譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とされるものは限定的です。
(1)具体的に認められる譲渡費用(非上場株式の場合)
株式売買仲介会社や投資銀行に支払った手数料
契約書作成やデューデリジェンスにかかる費用
株式譲渡契約書に貼る印紙税
例:株券の名義書換料、譲渡契約に伴う登記費用
(株式の場合ほぼ不要だが、会社法上必要であれば譲渡費用に含まれる。)
(2)認められない費用
譲渡費用として含めることが認められない費用は下記の通りとなります。
- 取得費に含まれるもの(購入時手数料など)
- 個人的経費(交通費や交際費など、譲渡に直接関係ない費用)
- 株式保有期間中の配当税や株式管理費
(3)譲受企業の諸費用の取扱い
譲受企業の諸費用のうち、取得の意思決定時点以後に発生した仲介会社への中間報酬や監査実施者への監査報酬などは、案件が成約すれば「関係会社株式」として株式取得代金と成功報酬とともに資産計上しますが、案件が破談すれば損金経理します。このように、案件の成約の可否によって処理方法は異なります。
7.M&A前の事前の株式取りまとめについて
非上場企業のM&Aでは、対象会社の株主が複数存在する場合が多く、そのまま譲渡契約を締結すると手続きが複雑になったり、後から株主の同意を得られなかったりするリスクがあります。
事前株式取りまとめの目的
事前株式の取りまとめの目的は下記の通りになります。
- 株主構成を整理し、譲渡対象株式を明確にする。
- 株主全員の譲渡承諾を得て、契約をスムーズに進める。
- 株式分散による交渉リスク・価値減少リスクを低減する。
実務上の流れについて
①株主リストの確認・整理
- 株主名簿・登記簿謄本を基に、現状株主の把握
- 未登記株式や相続・贈与で移転された株式も確認
- 株主間で争いがないか、株主契約・定款制限をチェック
②株式の買い取り・交換
- 少数株主がいる場合、事前に主要株主や会社が買い取るケースがある。
- 会社や主要株主が少数株を集約 → M&A後の買収がスムーズに
③株主間契約・譲渡承諾
- 株主間で譲渡承諾契約(Shareholders' Agreement)を締結
- 株式譲渡制限条項がある場合は、事前承諾が必要
④デューデリジェンス前の株式整理
- 投資銀行、M&A仲介がデューデリジェンスを行いやすくするために、株式の所有関係を事前に整理
- 株主数を絞ることで、価格交渉や契約交渉も効率化
買収者の立場に応じて変化する適性価額について
M&Aでの売買を除く個人間の非上場株式の売買の場合、財産評価基本通達による算出株価が適性価額とされて、買収者に立場に応じてその価額が異なります。
同族株主が買い取る場合
株式の買い手が会社や主要株主(議決権50%超)の同族であるため会社支配に影響せず、また市場性が低いため割引を控えめに評価するケースが多くなります。この場合、原則的評価額を適正価額として考えることが多いです。実務的には、この金額よりも低い旧額面金額等での買取りも行われていますが、この場合は同族株主側に原則的評価額との差額について贈与税の課税リスクがあります。
(計算方法)
会社の従業員数、純資産、売上高に応じて会社の規模区分を決定し、その区分に応じて、純資産と類似業種比準価額の2つの割合を変えて計算し、小規模な会社ほど純資産の割合を大きく、大規模な会社ほど類似業種比準価額の割合を大きくします。
少数株主が買い取る場合
少数株主は、会社の意思決定に影響できないため市場性が低い株式を取得することになり、適性価額は配当還元価額であるといえます。
(計算方法)
過去2年間の配当金額を基に計算して、通常は原則的評価額よりも低くなります。
(4)「90%以上保有株主」による株式の強制買取り
会社法上の「特別支配株主による株式等売渡請求制度」(会社法179条〜)の内容になります。いわゆる「スクイーズアウト」の一種で、M&Aや組織再編時に使われます。発行済株式総数の90%以上を保有する株主である特別支配株主が、会社を通じて他の少数株主に対し、自分に株式を売り渡すよう請求できる制度になります。要するに、少数株主は強制的に株式を現金化され、会社から退出させられる仕組みで、手続の流れは下記の通りです。
- ①特別支配株主が会社に対し、他の株主に売渡請求をするよう求める
- ②会社が各少数株主に通知(または公告)
通知内容:売渡請求を行う旨、買取価格、買取日など - ③少数株主は原則として拒否できず、指定日までに株式を特別支配株主に移転
- ④特別支配株主は少数株主に対し公正な価格を支払う
売価価格は、「公正な価格」でなければならない(会社法179条の8)とされており、類似業種比準価額方式や純資産価額方式、DCF法など将来収益を反映した方法が取られることが多いです。
また少数株主の救済として、価格に不服がある場合は、売渡株主は裁判所に「売渡株式の価格決定の申立て」をすることが可能です(会社法182条)。これによって、買取価格が公正かどうかを司法判断で争うことが可能となります。
8.まとめ
いかがでしたか?
株式譲渡所得の各種論点についてお話ししました。
この記事が皆様にとってお役に立てば幸いです。